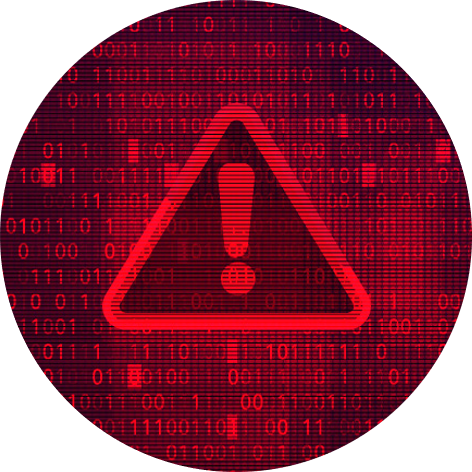
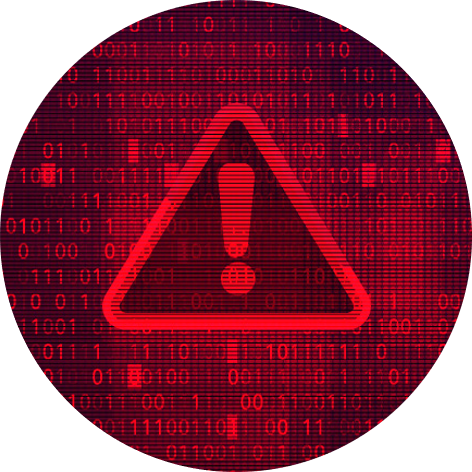
クレジットカードの申請をしたのに、なぜか却下された。理由を問い合わせても「AIの判断です」とだけ伝えられる──そんな経験をされた方が、これから増えていくかもしれません。 私たちの暮らしは、すでにAIという目に見えない技術に影響されはじめています。 そしてそのAIが、誰かにとっては利益をもたらし、別の誰かにとっては説明なき不利益を与える存在となっているのです。
アメリカの消費者金融保護局(CFPB)は、この新たな不平等にいち早く注目しました。 CFPBはAIが融資判断や信用スコアの算定に用いられる中で、偏ったデータや設計によって、マイノリティや低所得者が不当に不利な判断を受けている可能性を指摘しました。 とりわけ、クレジットカード関連の事例では「説明責任が不在のまま差別が生まれている」として、アルゴリズムの透明性と説明義務を求める規制の導入を進めようとしていたのです。 しかし、2025年、トランプ政権はこの流れを「過剰な官僚主義」として否定し、CFPBの機能を大幅に縮小させました。 同政権を支持するテクノロジー界の影響力ある人物、イーロン・マスク氏も「AIに対する過度な規制は、アメリカのイノベーションを損ない、中国などの競合国に遅れを取る危険がある」と主張しています。
では、AI規制の何がイノベーションを阻害すると懸念されているのでしょうか。
第一に、規制によってAI開発にかかるコストと時間が大きくなってしまう点が挙げられます。
企業が新しいAIシステムを導入するたびに、リスク評価・透明性確保・倫理審査など複雑な手続きを経る必要があれば、スタートアップや中小企業には過大な負担となります。
第二に、技術革新には試行錯誤が欠かせませんが、規制が先行しすぎると「失敗が許されない環境」が生まれ、開発者の挑戦意欲を削ぐおそれがあります。 たとえば「差別的な出力が出る可能性があるからAIを使わない」という判断が業界に広がれば、問題を解決するための研究そのものが止まってしまうかもしれません。
そして第三に、AIにおける国際競争です。規制の厳しい国では、慎重すぎる運用がデフォルトとなり、結果としてグローバル市場で後れを取るという不安があります。 技術は速く進化しますが、法律や制度はそれについていくのが難しい。だからこそ、「まず走って、問題が出たら直す」という柔軟なアプローチが必要だ、という主張にも一理あります。 ただし、これに真っ向から対抗する立場もあります。EUは2024年に「AI法(AI Act)」を制定し、AIをリスクレベルに応じて分類し、特に「高リスク」な用途──信用スコア、採用、教育、警察など──に対しては厳しい規制を課しました。 EUのスタンスは明確です。イノベーションは歓迎するが、それは人権や公正と両立しなければ意味がないということです。
つまり、EUが「社会全体の安心感」を重視するのに対し、アメリカのトランプ路線は「技術のスピードと市場のダイナミズム」を優先しているとも言えるでしょう。 どちらが正しいとは一概に言えません。イノベーションと規制のバランスは、非常に繊細な調整が必要です。
それでも、私たちが忘れてはならないのは、技術の進歩そのものが目的ではないということです。AIは人間の生活を豊かにするための手段であり、それが不透明さや差別を助長するものであってはなりません。 CFPBが目指したのは、AIに「人間らしさ」の基準を持ち込むことでした。単に開発の足を引っ張る存在ではなく、信頼と持続性のある未来をつくるためのセーフティネットだったのです。
AIが誰の味方になるのか。それは、その技術にどんな価値観を組み込むのかにかかっています。公正さとスピードの間で揺れる今こそ、その問いにしっかりと向き合う時ではないでしょうか。
種明かしです。
時流に乗ってAIにエッセイを書かせてみました。要したプロンプトはけっこうな量でしたが、それにしても驚くべき生産性の高さです。AIさん聞きしに勝る賢さですね(笑)。
せっかくなので人間であるわたし園田が(笑)このコラムに追記してみましょう。
AIの規制と技術の進歩というものに向き合うわれわれにとって、無視できないもう一つのライバルは犯罪業界です。かれらは規制があっても無視しますし、法律も関係ありませんし、公共性なんてものも無縁です。 したがって思うがままに研究開発を行えますし、倫理という心理的な制約からも自由に発想できるので、もしかしたら世界最高レベルの実験性でAIを進化させられるかもしれない、そういう環境にあるわけです。 規制は人権の保護としても非常に重要だと思いますが、それが存在するがゆえに、法律や規制があるため犯罪者達に比べて非常に制約的にテクノロジーを活用せざるを得ない現状と同様に、ある意味の負け戦が再現してしまうかもしれません。 そこには危機感を抱かざるを得ません。
幸い、犯罪業界の研究開発力は人員リソース的にも発想力的にもそれ以外の業界の総合的な研究開発力には遠く及びません。 ただ、表の世界で研究成果がオープンであるなら、それを活用することができてしまうわけですし、国の後押しがある場合などはもっと大々的にいろいろできちゃうこともあるでしょう。 決して油断はできない状況です。とはいえ規制も重要、となるとわれわれはどうすれば良いのでしょうか(笑)?
われわれはおそらく、今以上にガッツリと力を入れて研究開発を進めていくべきだと思います。研究者を十分保護しながら、発想を発揮してもらう。
危険な研究が必要ならばそれを可能とする環境を整え、バックアップし、研究成果の流通には社会として十分注意を払う。核兵器開発がカジュアルになったときの二の舞はしない。
大国によるエゴイスティックな情報統制と不平等に少々近視眼的な怒りを覚えた科学者のリーク、という不幸な図式にはならないように、良識的な情報統制を行う。そのあたりも必要でしょう。
・・・・・・書いていて到底実現できるような気がしませんが(笑)、それでも必要だと言いたいですね。
しかし、そのような環境を整備できたとしたら、学界と対立的で予算を奪おうとしているトランプ政権のアメリカから逃げ出してくる超優秀な科学者研究者たちを大量に迎え入れることができるかもしれませんね(笑)。